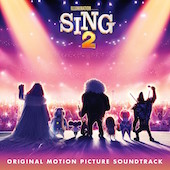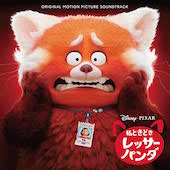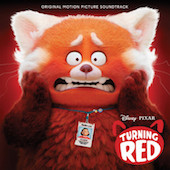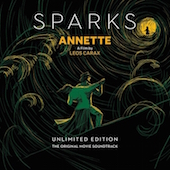| ||||||||||||||||||
  |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■「シング:ネクストステージ - オリジナル・サウンドトラック」
| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
国内盤CDも発売されるようだが,映画公開日に同時発売で,本稿執筆時(3/15)はまだ入手できていない。このため,国際盤の17曲入りを頼りに本稿を書いている。国内盤はボーナストラックが沢山入り,25曲収録とアナウンスされている。それでも映画本編中の41曲よりかなり少ないが,短くしか流れなかった曲をカットしたのだろう。その反面,映画中にはなかった“Christmas (Baby Please Come Home)が入っていて,主要キャスト一同が歌っている。米国ではXmasシーズンの公開&発売ゆえのボーナスだろう。 | |||||||||||||||||||||
■「私ときどきレッサーパンダ(オリジナル・サウンドトラック)」
| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| こちらも国内版(日本版)が出ているが,国際版より1曲多いだけの33曲構成だ。最近の傾向らしく,いずれもCD発売はなく,ネット配信だけで入手できる。国際版での歌唱曲は3曲で,とその別バーションの計4曲で,すべて売れっ子シンガーソングライターのBillie Eilishと兄のFinneas O'Connellが,この映画のために書き下ろした新曲である。残りは,Ludwig Goranssonによる劇伴のオリジナルスコアだ。 もう少し詳しく言うなら,上記3曲は“Nobody Like U”“1 True Love”“U Know What’s Up”で,歌唱曲の他に各々のカラオケも最後に付されている。さらに“U Know What’s Up”だけ,(The Panda Hustle Version)なるものが入っている。注目すべきは,その4曲にアーティストとしてクレジットされているのは,劇中に登場する架空のグループ「4★TOWN」である。声優に歌わせたのか,別のプロ歌手なのかは不明だ。劇中での彼らのセリフは少ないので,おそらく,先に歌唱するグループを決めておき,そのメンバーに声の出演もさせているのだと想像する。 各国の国内版の1曲目は,主題歌の“Nobody Like U”をそれぞれの言語で歌わせる方法を採っている。日本の場合,ダンス&ヴォーカルグループDa-iCE(ダイス)が日本語で歌い,映画内で対応するメンバーの声の出演も務めている。20歳前後の若者かと思ったら,5人中4人は30歳以上だった。筆者がこの年代の音楽に疎いため,ようやく昨年末にレコード大賞を受賞したことを知った程度だが,2011年デビューのグループで,丁度5人組ということで抜擢されたようだ。こうしたメジャー作品への起用で,さらに知名度が上がることだろう。 一曲追加だけだから,アルバムもジャケットもほぼ同じで,題名が日本語になっているだけである。眺めて楽しかったのは中国版だ。中国では,この映画の題名は「青春養成記」と言うらしい。「赤色」も「レッサーパンダ」なる言葉も出て来ない。「Original Motion Picture Soundtrack」が「中文版電影原聲帯」と書かれているのを見て,そーか「Soundtrack」は「聲帯」というのかと,妙に感心してしまった。 そうした工夫はあるものの,サントラ盤としてのクオリティは,「シング:ネクストステージ」の圧勝だと思う。 | |||||||||||||||||||||
■「Annette - Cannes Edition (Selections From The Motion Picture Soundtrack)」 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 異色のミュージカル映画『アネット』のサントラ盤で,これが2種類ある。1つは上記のタイトルの「Selections」で分かるように,このミュージカルの肝となる代表的シーンの抜粋で,もう1つは「Annette (Unlimited Edition)」と呼ばれている完全版である。所謂,「ソング版」と「ソング版+スコア版」ではない。何しろ,ラストシーンを除いて全編で歌い続けているのだから,歌唱部分だけを抜粋するということにはならない。 前者は15曲構成,約41分間で,「Cannes Edition(カンヌ版)」と呼ばれている。正確な意味は知らないが,カンヌ国際映画祭の審査時かプレス対策で,この抜粋版を配ったのかと想像している。国内販売で“「アネット」オリジナル・サウンドトラック”と呼ばれているのは,このカンヌ版のことである。デジタル配信だけでなく,CDも(限定生産であるが)LP盤も存在している。後者の「Unlimited Edition」は,ほぼ無音でセリフ(歌唱)のない部分を除いた映画のほぼ全編に加え,Demo版6曲も収録した全63曲構成で,CDは2枚組である。 内容に関しては,素人同然で,筆者にそれを論評する資格があるのか疑わしいが,同じレベルの読者のために,映画紹介の補足を兼ねて,個人的感想を述べておこう。 まずは,米国のロック・バンドのSparks。ロン&ラッセル・メイルの兄弟によるバンドで,1967年に活動開始し,1970年にこのバンド名にしたというから,既に半世紀以上の活動歴である。兄のロンは1948年生まれというから,筆者とほぼ同世代だ。1970年代中期に電子音楽を指向した頃に,少し聴いた覚えはあるが,この時点で全くついて行けなかった。その後,グラムロック,サイケデリック・ポップ,エレクトロニック・ダンス・ミュージック等へも進出し,「エレクトロニック・ポップ・デュオ」なる形態を生み出したとされているが,全く聴く気になれなかった。常に新しい趣向を凝らすバンドで,カルト的人気を維持し,その意味ではポップ&ロック業界でも一目おかれる存在ではあるらしい。 一方のレオン・カラックス監督も,Sparksに劣らぬ完璧主義者の異端児であり,映画業界でも寡作でその名を知られる。長編デビューが1983年でありながら,本作『アネット』がまだ6作目ということからも分かるだろう。デビュー当時,並び称せられたリュック・ベッソンとは,随分,路線も実績も違ってしまったなと感じる。代表作『ボーイ・ミーツ・ガール』(84)が話題になっていたが,数年間本邦での公開がなかったので諦めた(当時はまだビデオレンタルが存在していなかった)。その後も長編は観る機会がなかったのだが,オムニバス映画『 TOKYO!』(08年9月号)の中で,彼の中編を観ている。当時の評では,「筆者はこの種のテイストは好きになれない。強いて言えば,2本目の『メルド』の下品さが少しだけ気に入った」と書いている。それが,かのL・カラックス作品であった。という訳で,初めて本作でこの監督の長編映画を観る機会がやってきた次第である。 音楽も映画も,およそ筆者の嗜好とは合わないはずなのに,この異端児同士のコラボが奏功したのだろう。不思議にも映画は素直に観ることができた。強烈なヴィジュアルと,主人公のアネットが生身の俳優でなく「人形」という異端ぶりに圧倒されていたとも言える。ヴィジュアルの方が気になって,音楽を味わう余裕は殆どなかった。 その後,(カンヌ版の)サントラ盤を聴いたところ,これが実に気持ちがいい。ブロードウェイ・ミュージカルの音楽とは一線を画しているし,古典的なオペラのように敷居が高くもない。なるほど,「ロック・オペラ」はこういうものかと実感できる。BGMとしてかけておいても心地が良い。作曲はすべてSparksで,作詞の一部はL・カラックス監督担当だという。歌詞=セリフなのだから,当然のことだろう。基本的には曲自体が良質で,物語を盛り上がる効果音とのバランスも絶妙に調整されている。全体で1つの物語であるので,特に気に入りの曲は存在しない。 主演のマリオン・コティヤールの歌唱力には定評があったが,もう1人の主演のアダム・トライバーがSparksの歌をまともに歌えるのかとの懸念もあった。実際には,何ら心配はなかった。A・ドライバー演じるヘンリーは,オペラ界のスター歌手アンと恋に落ちて結婚したコメディアンという役柄であるから,まともな歌唱シーンは殆ど登場しない。せいぜい大げさな抑揚をつけたセリフの範疇を出ない。それなら抜群の演技力を誇る彼なら難なく演じることができる。 この長身の男優は,『パターソン』(2017年9月号)で注目したのだが,『スター・ウォーズ EP7〜EP9』で大役カイロ・レンに抜擢され,その後も主演級の作品が続いている。本作は,『マリッジ・ストーリー』(19年Web専用#6)の後,『最後の決闘裁判』(21年Web専用#5)『 ハウス・オブ・グッチ』(22年Web専用#1)より前に撮影されたようだが,硬軟取り混ぜた様々な役を見事に演じ分けている。本作も,彼の芸域を拡げる一作になったと言えるだろう。 | |||||||||||||||||||||
| ( |
|||||||||||||||||||||
| [本欄は,O plus E誌掲載稿に大幅加筆し,「アネット」のサントラ盤紹介を加えています] | |||||||||||||||||||||
| ▲ Page Top | |||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||