�R���s���[�^�C���[�W�t�����e�B�A���� �ҁi����2�j
ISMR'99��
�o�[�`�����ƃ��A���̎��_�i���j
O plus E, Vol.21, No.9, pp.1178-1187, 1999
�@��S�� �o���P�b�g�F�R���q�����đ喞��
�@�`�[�Y�E�X�p�Q�b�e�B����i ���̃V���|�W�E���̂�����̃n�C���C�g�́C�Q���ڂ̖�̃o���P�b�g�Ƃ���ɑ��������ł̓��� �u���ł����B
�@�Ă�����V���|�W�E�����ɗאڂ����C���^�[�R���`�l���^���E�z�e���ŊJ�����̂��Ǝv���Ă�����C�������ꂽ�p���p�V�t�B�b�N�E�z�e���̒n���Q�K�ւƗU������܂����B���ؒ��w�ɖ߂�r���̃N�B�[���Y�E�X�N�G�A�̈ꕔ�ɂ���V�����z�e���ł��B�C�ɖ� �����C���^�[�R���`�l���^���ƁC���т��郉���h�}�[�N�E�^���[�̒��ɂ���z�e�����q�̒��ԂɈ� �u���Ă��邽�߂��܂�ڗ����܂��C�쉢���̂ƂĂ��I�V�����ȃz�e���ł����B������܂肵�Ă���Ǝv�����̂ɁC�n���Q�K�̉����͍L�X�Ƃ��Ă��܂����B�V����������������ł��B
�@�������\�z�𗠐��đ�D�]�������̂́C���̗����̎��Ɨʂł��B�O��̃��Z�v�V�����̗����������Ƃ����ԂɂȂ��Ȃ����̂Ŋ��҂��Ă��Ȃ������̂ł����C�����ɂ��ǂ����ɊO��܂����B�Ƃɂ������������������ƁI ������Ɗw��̃o���P�b�g�Ŗ��킦��N�I���e�B�ł͂���܂���B�ǂ̗������C�f�U�[�g�Ɏ���܂Ŋ����ł����B���M���ׂ��́C�`�[�Y�E�X�p�Q�b�e�B�ł��傤�B��l������䥂ł��ẴX�p�Q�b�e�B���{�E����̃`�[�Y���ɐZ���Ē������Ă����̂ł��B���̖��͂��܂ł��Y��Ȃ��ł��傤�B�o�C�L���O�E�X�^�C���ł������C�F�����x�����ɍs���Ă��\���Ȃ����̗� ������܂����B���̃z�e���́C�O�����c�A�[�ɂ����X�X���ł��B
�@�܂��܂��^�E���K�C�h���ɂȂ��Ă��܂��܂������C�H���̖������͎Q���҂̐S��a�܂��C�������������ɂȂ�܂��B�o�C�L���O�����Ȃ�������H�ł͂Ȃ��C�~��ɍ���X�^�C���������̂��D�������Ă܂����i�� �^�P�j�B���M���������܂܉�b����͔̂��邵�C��ʒu�ɒ��Ȃ��Ẵt���R�[�X�͘b���l�������Ă��܂��܂��B�K�x�ɋ�Ȃ�����C�e�[�u����n������l�����Ȃ��Ȃ��C���̓_�ł����̃o���P�b�g�͑听���������悤�ł��B
 �ʐ^�P�@�o���P�b�g��� |
�@�����ȉ��o�̓��ʍu��
�@�������ɂЂ���C���낻��b����ꂽ���C���̏Ɩ������ׂď����܂����B��u�����낤�Ǝv���Ęb�������~�ނƁC���X�Ƀ��C�g�A�b�v���Ă����āC�i��҂���u���ƂT���ŁCDr. Ishii��Special Talk���n�܂�̂ŁC���̂����ɃR�[�q�[�ƃf�U�[�g�����ɍs���܂��傤�v�Ƃ̃A�i�E���X�ł��B�Ȃ��Ȃ��S�������o�ł��ˁB
�@�f�U�[�g�R��ނ��d����ĐȂɖ߂�ƁCMIT���f�B�A���{�̐Έ�T�搶�́uTangible Bits: Coupling Physicality and Virtuality Through Tangible User Interfaces�v�Ƒ肵������ �u�����n�܂�܂����B�o���P�b�g�ł̍u���ɂ́CSocial Talk�Ə̂��āC�悭�n�����m�̎s�������`���H�|�ƂȂǂ��b������܂��B����Ɣ�ׂ�ƁC�o���o�������̌����҂ŁC����ł��Ă����������͋C�Ƀ}�b�`�����y���������߂ɂȂ邨�b�ł����B
�@����CIF�V���[�Y�̓ǎ҂́C�����Έ�搶�̂��Ƃ͂悭�䑶�m�̂͂��ł��B97�N3�����́u���̌Q���T�v�ɓo�ꂵ�Ă���ꂽ���C97�N8�����ł́C���́u�^���W�u���E�r�b�c�v���̂��̂��e�[�}�Ƃ����C���^�r���[������܂����B���́C�\�߂��̊T�O�����Ă����̂ŁC�u���ɂ�����Ȃ�����čs���C�ŐV�̌������� �̂��݂��݂܂ŏ\���ɗ����ł��܂����B���{�l�̉p��䂦�ɕ����₷���������Ƃ��v���X���Ă��܂��B���x�����Ă��V��������������̂́C��قǂ��̃R���Z�v�g�ƍu���̍��g�݂��������肵�Ă��邩��ł��傤�B
�@���̃��N�`���[�́C�u�^���W�u���E�r�b�c�v�̃R���Z�v�g�����߂ĕ����l�ɂ�������₷���C��D�]�ł����B���݂�GUI�ɖO�����炸�C�l�ԂƂ̕����I�Ȑړ_�����߂�Ƃ����A�v���[�`�́C�ǂ��ōu��������Ă��傫�ȋ������ĂԂ悤�ł��B��N���獡�N�ɂ����āCSIGCHI�CSIGGRAPH�Ő������̘_����r�f�I�\����Ă��܂��B���̏����Ȑg�̂ŁC�@�֏e�̂悤�ɏo�Ă��錾�t�ƁC�p���t���Ȃ��d���Ԃ�ɂ́C�قƂقƊ��S���Ă��܂��܂��B
�@���̐l�I�����e���CISMR'99�����{�����������Ȃ����ۃ��x���̌����W��ł��邱�Ƃ���Ă��܂����B����ł��āC�T�[�r�X���_���炩�C���̓��� �u���͓����ʖȂ��̂ɁC���{��ł̎��₪������Ă��܂����B�Έ�搶�����{�ꎿ����p��Ŕ������C�p��œ�����ꂽ�̂ł��B���̂������ŁC���{�l����������ȃj���A���X�̎��₪��������o�āC�傢�ɐ���オ��܂����B���̎��^�̓��e���C�p��Ɠ��{��ōČ������E�F�u�T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B
�@�����ƍu�����e�Ɖ��^�c�������ɗn�������C3���q�������n�C�N�I���e�B�̃o���P�b�g�ɑ傢�ɖ����������ł����B �@�@�@�@�@�@�@�i![]() �j �@
�j �@
���䗠�S �A�C�f�A�G���Ə������̏�
�@�r���E�Q�C�c�ɒǂ��o���ꂽ
�@�����ƃo���P�b�g���Ɨ������D�]�������悤�����C����̓P�K�̌����ł���B�����C�t���A�����̃C���^�[�R���`�l���^���E�z�e���Ɋm�ۂ����o���P�b�g���́C�l�������`���āC�����������Ɍ��߂Ă��܂����B�J�Â��߂Â��Ċm�F�ɍs���ƁC���ꂵ���Ă������ƃe�[�u��������ꂻ���ɂȂ��B�V����Ⴍ�C�v���[���p�̑傫�ȃX�N���[����u�������ɂȂ��B���܂��ɉ��̒��ɉ��{�����������āC����ł͌���̐Ȃ���̓X�N���[���������Ȃ��B���� �̗��H�p�[�e�B�Ȃ�C����ł������Ȑl�����l�ߍ��߂�̂ŁC�z�e���͂���������U���Ă����̂��낤���C����ł͖ړI��Evening Plenary�u���͂��Ȃ��B
�@�ʂɗ��h�Ȏ剃��ꂪ����̂����炻����ֈڂ��Ă���Ɨ����C�z�e������͉������Ȃ��B����Ȃ�C�ׂ̃p���p�V�t�B�b�N�E�z�e���Ɉڂ邼�Ƌ�������C�������ɐ^�� �ڂɉ����Ă������C���ǂ͒f���Ă��܂����B�ǂ����c�Ə�C�V���ɂ������Ă����悤�ŁC�剃���̃{�[�����[���͕� �̉�c�̃o���P�b�g�Ɏ���Ă��܂����B������c�Z���^�[�̕ʃt���A�ŊJ�Â���Ă����}�C�N���\�t�g�Ђ̃f�x���b�p�[�p�̃R���t�@�����X�ł���B
�@���̃f�x���b�p�[�Y�E�R���t�@�����X�ɂ͐����ς킳��Ă��܂����B������l�����Ⴄ�B�r���E�Q�C�c�̓��� �u�����G�T�ɁC2,000�l�ȏ���W�߂Ă����悤���B�������i�̃A�i�E���X�Ƃ�����Ƃ����u�K�ŁC���\�ȎQ���������C���ꂾ���̐l�����W�߂�̂�����C�r�W�l�X����̈З͂͂������B
�@�P�K�̃��r�[�ł́C������̎Q���҂����C�Ŏ����̕��Ăэ��ނȂǁC���̉�c�̑��݂Ȃǂ܂�Ŗ����̖T�ᖳ�l�Ԃ�ł���B�w�p�n�̉�c�̑��݂Ȃǂɖڂ�����Ȃ��̂́C�ŋ߂̃R���s���[�^�E�T�C�G���X��PC�ƊE�̊W���ے����Ă��邩�̂悤���B���ɂ��C���낢�돬���ȃg���u�����������炵���B�V���N�Ȃ̂ŁC�r���E�Q�C�c��f�v���ė��āC������ōu�������悤���Ƃ̘b���o�����C�����������ɂ��Ęb�������Ȃ��̂Œf�O�����B
�@�b�x��B����Ȃ킯�ŁC�p���p�V�t�B�b�N�E�z�e���Ɉڂ����̂����C���ꂪ�吳���������B���{VR�w��̉�c�ŁC�u����Ȃ蕱�������Ǝv���闿�����~��ł������Ɗy���ނ��Ƃ��ł����v�Ə�����Ă��܂������C����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�����펯�I�ȉ��i�Ȃ̂ɁC�v���������������������ł���B�o�ȗ��̗\�z������C���o�^���̂��ɕ����肪��∫���C���� �I�ɗ����ɂ��Ȃɂ��]�T���ł��Ă��܂����B
�@�v���O�����\���C�\�e�_���W�Ɠ����ȏ�ɁC�o���P�b�g�̏[���ɋC��z�������Ƃ͎����ł���B���l���̃N���[�Y�h�ȃZ�~�i�[�̏ꍇ�C��̕��̌𗬉�͒��Ԃ̉�c�ȏ�ɏd�v�ȃC�x���g�ł���B��� ���J�X�^�C���ɂ����Ƃ͂����C�I�[�����E�Z�b�V�����͑S���ҍu���Ƃ����ȏ�C�C�O����̏��ҍu���҂��͂�ł̌�����̓��x���_�E���������Ȃ������B���ƂɁCMR�Z�p�̂悤�ɁC�Z���T��C���^���N�e�B�u�E�f�o�C�X���d�v�Ȗ���������ꍇ�́C�_�����\�������낢����ł̏��������傫�ȈӖ������B�E�F�u�ł̏����W������ł��邪�C�Ő�[�̏��̓i�}�Ɍ���B�ŋ߂̎Ⴂ�l�����͂��܂荧�e��ɏo�悤�Ƃ��Ȃ����C�����ҁ^�Z�p�҂Ȃ�C���t�H�[�}���ȏ�œ�������̑���ɋC�t���ׂ����Ǝv���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i![]() �j
�j
�@���܂ł��c�����]�C
�@Evening Plenary�ɐΈ�T���������ė��邱�Ƃ́C���̃V���|�W�E������悵��������l���Ă����B�C�O�Ŋ�����{�l�Ƃ����̂́C�ł����{�̒��O���W�߂₷�����C���������W�q�͂����C�L�`��Augmented Reality�ɑ�����ނ̎a�V�ȃR���Z�v�g�����C���̃o���P�b�g�̏�ɑ��������Ǝv�����̂ł���B
�@�ނ̌����̐i�W�́C�C��n���ă��f�B�A���{�֍s���Ĉȗ������ƃE�H�b�`���Ă���B�ނ̃p���[�ƌ���S�Ȃ�C���Ȃ��邾�낤�Ǝv���Ă������C���������Ă����܂Ŋ���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�債�����̂ł���B�ŋ߂́C���������̊w��珵�҂���A�����邱�Ƃ������Ȃ̂ŁC��e�[�}�I�V�N���͔���Ă��邩�ƌ��O�������C���̕��m���x�����サ�Ă����B��䎁�ɕ�������炸�����t�@���������Ƃ����i�������I�j�B���̃o���P�b�g�E�Z�b�V���������ɎQ���������Ƃ����\���݂��������B
�@�����˘f�����̂́C���̐Έ䎁���u�l�����̂�H�ׂĂ��鎞�ɘb�������Ȃ��v�ƌ����o�����̂ł���B�S�g�S����X�������N�`���[�ɂ���̂ŁC���������ő���̒��ӂ��ĕ����ė~�����C�Ƃ������Ƃ炵���B�����y�ڂ̟��E�Șb���������Č���Ă��������Ǝv�����̂����C���̃G�l���M�[�̉�̂悤�Ȑl���ɁC����͖����Ȃ悤���B���h�ȉ��Ƒ傫�ȃX�N���[����p�ӂ��邱�ƁC�قڐH�����I����Ă���X�^�[�g���邱�Ƃ������Ƀo���P�b�g���ł̓��� �u����ȏ����Ă�������B
�@�u�����f�U�[�g��R�[�q�[�����ɍs�����O�����\����̂ł͂Ǝv�������C�F���ɋ߂������B�Έ䎁�̘b�p�ƃX�g�[���[���̍I�݂��ɊF��������āC�N���Ȃ𗧂��Ƃ��炵�Ȃ������̂ł���B�X���C�h���S�ŁC�r���r�f�I�͂V�`�W�{��f���ꂽ�B���̐�ւ��̃^�C�����O���������C�X���C�h�ɂ��r�f�I���X�[�p�[�C���|�[�Y�����f�B�]���u���� �������ł������B
�@�u���I����̎��^��30���߂����������낤���B���܂ł��]�C�����߂�炸�C�U�����ނ̂܂��ɐl�_���ł��Ă����B�����A�C�f�A�͊���O�ɕ����Ԃ��Ƃ͂��܂�Ȃ��C�������������̏�Œm�I�h�����G������邱�Ƃ����X����B�u�A���r�G���g�E���[���v�u�s���|���E�v���X�v�u�C���^�b�`�v�u�E�H�[�^�[�E�����v�v�u�s���z�B�[���v�u�~���[�W�b�N�E�{�g���v���X�C��p�������ɏo���ꂽ�u�^���W�u���E�r�b�c�v�̐��X�̌������� �́C�Ⴂ�����ҒB��傢�ɐG�������ɈႢ�Ȃ��B
�@�u�Έ䂳��̘b�͂����ʔ����ˁB�����d�������C�悭�l���Ă�ˁv�Ƃ́C��u���҂̋��o���Y�����̊��z�ł���B�����C�Έ䎁�ɓ`������C���Ƃ̂ق����ł����B��͂�C�č��̒�����w�Ő��������߂����҂ɗ_�߂�ꂽ�̂��C�����������������悤���B ��T�� �|�X�^�[���f����MR���c�A�[�F�����ԃf���̋M�d�ȑ̌�
�@���{�̎��͂��A�s�[��
�@2���ڂ̌ߌ�CMR�v���W�F�N�g�̒��Ԑ��ʔ��\�̌�̓t���[�^�C���ŁCMR���ւ̃c�A�[�Ɖ��ł̃|�X�^�[���\�ƋZ�p�f���W�������R�Ɍ��ĉ���悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�|�X�^�[��11���i�P���̓L�����Z���j�C�f���W���͂V���C�����������ŏW�܂������̂ł��B���ҍu���҂����܂�ɂ���т₩�Ȃ̂Ŗڗ����܂��C�|�X�^�[���f�������Ȃ�[�������ŐV�̓��e�ł����i�� �^2�j�B
 �ʐ^�Q�@�|�X�^�[��� | 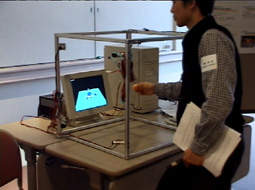 �ʐ^�R�@�Z�p�f���W���̕��i |
�@�|�X�^�[���\�̒��ł́C��̕\��\���Ɋւ���MR�Z�p��2���i�����ّ�w�C������w�j���������ƁCATR�ł͑�|����ȑ��u�����ĉ��� �̂���l�ʂ̕��s�̃��A���e�B�����������Ă��邱�Ƃ���ۓI�������B�C�O����̎Q���҂͂��܂葽���Ȃ��͂��Ȃ̂ɁC�|�X�^�[�ŔM�S�Ɏ�������Ă���̂͊O���l���ڗ����܂����B���{�l�̔��\�ɑ����{�l���p��Ŏ��₷��̂��C�p���������̂��C���邢�͂܂����ł�������Ǝv��������������܂���B
�@�Z�p�f�������Ȃ�[�����Ă��܂����i�ʐ^3�j�B���V���g����w��ޗǐ�[��̃V�X�e���́C���ҍu���ł����\���ꂽ���̂ŁC���x�������������悤�ł��B�ޗǐ�[��̍����G��搶�́C�E�F�A���Ԃ��AR�V�X�e���ꎮ����������ł����C����w�̉����������͑S���^�̉f�����B���Hyper Omni Vision�J������W�����Ă����܂����B���j�[�N�ȗ͊o�C���^�t�F�[�X�Ƃ��Ēm���铌�H�卲����������SPIDAR�́C����̓W���ł͓��I�ȑΏۂ���������悤�Ɋg������Ă��܂����B
�@MR�v���W�F�N�g�ȊO�ł��C���ꂾ���������蓮���V�X�e�������������݂��Ă��邱�Ƃɋ����܂����B����͊C�O����̎Q���҂ɂƂ��Ă������ŁC�u���{�ŁC���̕���̌������C���ꂾ���̃{�����[���Ői��ł���Ƃ͒m��Ȃ������v�Ɗ��S���ꂽ�悤�ł��B
�@MR���ւ̃c�A�[�́C��30�������ɃV���g���E�o�X���^�s����Ă��܂����B�v���������߂��C���̃o�X��10�����̋����Ȃ̂ł��B�Ȃ�قǁC�p�V�t�B�R���l�����ɂȂ��Ă������R���悤�₭�����ł��܂����B
�@���ҍu����|�X�^�[���f���̕\��́C���ł��E�F�u�y�[�W�ɍڂ��Ă��܂����C�l�q���̃f���ɂ��Ă͋L�ڂ��Ȃ��̂ŁC�\�P�ɂ����Ă����܂��傤�B���̑��ɁC�V�����g�l�c�ƃ��K�l�Ȃ����̃f�B�X�v���C���W������Ă��܂����BMR�����̂��̂̌������� �̑��ɁC���������̓���E�A���������C�}�g��E��c�������̍�i���ғ����Ă��܂����B�����Ȃ̂ł��B�D�y�����ł̌������e���p�l���W������Ă���ȊO�́C�����ɓW������Ă���̂́C����������ۂɓ����Ă��āC�ϋq���炪�̌��ł�����̂Ȃ̂ł��B �@���̑̌������͍u�����Ă��_����ǂ�ł������Ȃ��̂ʼn��l������܂��B����������p�҂̎��_�Ŏ����ԑ̌��ł�����̂����ɏ��X�ł��B
| �\1 MR�V�X�e�����������w�c�A�[�̃f���ꗗ |
| |
MR Living Room�`���������C���e���A�V�~�����[�V���� �Ƌ�̔z�u����������̂ɁC�����d���Ƌ�����K�v�͂���܂���D�����̋�ԓ��ŃV�[ �X���[HMD�����Ԃ�C�������E�ɃI�[�o���b�v���ĉ��z�̃C���e���A������܂��D���� �Θb�ɂ��C���z��ԓ��̃G�[�W�F���g�ɍ�Ƃ��w�����邱�Ƃ��ł��܂��D����܂ŁC�C ���[�W�r�f�I�Ō��Ă��������������������E���C���̌��ł���悤�ɂ��܂����D�������E �Ɖ��z���E�̈ʒu���킹�ɉ����āC�掿�I�Ȑ��������l�����������������V�X�e���̍\�z ��ł��D |
| |
RV-Border Guards�`���l�������^�����������Q�[��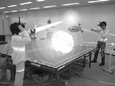 ��N��SIGGRAPH'98�ōD�]����AR2�z�b�P�[�i�����^�����������Q�[���j�W���� �����̂ł��D�V�[�X���[HMD�����C�������E�̑ΐ�҂����F���Ȃ���C���z�̕��̂� ���Ă������V���[�e�B���O�E�Q�[���ł��D�����������V�X�e�����l�ŋ�������ł��� �悤�ɂ������̂ŁC�V�X�e���̐��\�E�掿�����コ���Ȃ���C�R���ȏ�ő̌��ł���V�X �e�����Z�p�Ɏ��g�݂܂����D |
| |
| Wisteria World�`�l�q�e���v���[���X�V�X�e�� �@ |
| |
| Cybercity Walker�i������w�E�A���������S���j
|
| |
| �e�[�u�������i�}�g��w�E��c�������S���j |
| |
�@�~�j�E�e�[�}�p�[�N�̌�
�@Cybercity Walker �́C�A���ʍF�搶�̂��u���ɑ��āC��u���҂�H. �t�b�N�X�搶�����̒��z���ƂĂ��_�߂Ă����܂����B���S���l���̊X���݂����� �Ŋۂ��Ɖ��z��Ԃɓ���Ă��܂��Ƃ����̂́C�X�P�[���̑傫�Ȃ��d���ł��B�������̗� �����������ƍL���̈悪����̂ł��傤�B�u���̃r�f�I���\�P�̎ʐ^�������w�O�̊ۂ̓��n��ɂȂ��Ă��܂����C�����̃f���̓V���|�W�E�����O�́u�݂ȂƂ݂炢�n��v�ŁC�傢�ɃE�P�Ă��܂����B�����O�ɃV���g���o�X�Œ� ���Ă����X���݂��Ǒ̌��ł����̂ŁC�܂��܂����̃��A�����i���ׂĎ��ʂ�����C������O�H�j���꒪�ł����B
�@�����̃p�l�����_�ŁC�q. ���C���o�[�O�搶�iUSC�j�����܂���Ă����̂́C�͌^�̊X���݂��w���R�v�^�[�𑀏c���銴�o�ō~��čs��Wisteria
World�ŁC���������R�m�V�搶�i�f�W�^���n���E�b�h�j�����S���Ă���ꂽ�̂͂R�l�őΐ킷��RV-Border Guards�ł��B���|�I�ȕ]�����Ă�ł����̂́C��҂̐V���������������Q�[���ł����C�c�O�Ȃ���҂��s�����C�̌��ł��܂���ł����B
�@�����C�Z�p�I�Ɋ��S�����̂́CMR Living Room�ł��B�����̃��r���O���[���ɉ��z�̃C���e���A���d�˂��킹��A�v���P�[�V�����ł��B���́C��N�̂U���̃I�[�v���n�E�X�ɍs�������ɂ��������̂ł����C�܂��J����Ԃ��Ȃ����̃o�[�W�����������炵���C���܂�ǎ��̕��������̌��ł͂���܂���ł����B�Î~���Ă���͂��̉��z���̂��t���t���Ɨh���̂ł��B�����C�n�k�̉��z�̌������Ă��邩�̂悤�ł����B����̃f���ł́C���̗h��͂Ȃ��Ȃ�C�� �u���킹���x�������ɉ��P����Ă��܂����B�r�f�I�V�[�X���[�̃J�����̌�����`������HMD�̌�������v���Ă��ė��̊������サ�Ă��܂��B
�@�����āC���������������̂́C�����Θb���ł���������{�b�g��̃G�[�W�F���g���o�ė��āC�����肵�Ă��ꂽ���Ƃł��B���ɕ����Č�肩���Ă���l�q�́C�f�B�Y�j�[�f��́w�t���o�[�x�ɏo�Ă���鏑�i�y�b�g�H�j���{�b�g�����������܂����B�L�����̓������ǂ��C���������̃N�I���e�B�������悤�Ɋ����܂����B���̎�̃G�[�W�F���g�Z�p�ɂ��ẮCCIF�R�V���[�Y�̑�W��i97�N12�����j�Ƒ�9��i98�N1�����j�ʼn������Ă��܂��B�� ��̃G�[�W�F���g���R���s���[�^�E���j�^�[��ʒ��̎l�p�����̒��ɓo�^����̂ɑ��āC����MR�G�[�W�F���g�͕���������Ԃ̒������R�Ɉړ��ł���̂������Ƃ̂��Ƃł��B�Ȃ�قǁCHMD�����Ăǂ���̕����������Ă��C����Ȃ�ɒǐ����Ă��܂����B����������Ԃ̒��ł̎p�E�`�̂���G�[�W�F���g�Ƃ����̂́C�q���[�}���C���^�t�F�[�X�������炷��ƂƂĂ������[���ΏۂɂȂ�Ɗ����܂����B
�@�ǂ̃f�����y�����ʔ����C�����������e�[�}�p�[�N�┎����ł����g�������Ɗ��������郌�x���ɒB���Ă����悤�Ɏv���܂��B �@�i![]() �j
�j
�@���䗠�T �f�������̘J�͂ƌ��� �قǂ悢����ň���S
�@���̎�̉�c�́C�Q������Ē��u���Ă�������y�ŁC��Îґ��ɉ��Ɖ����ƋC��J�������B���\���e�̃��x�������邱�ƂȂ���C�Ɩ��≹���C�ē���W�����̔z�u�����Q���҂̐S���I�����x�ɑ傢�ɉe������B���ׂĂ�������ʼn��o�E����ł���Ȃ炢���̂����C�|�X�^�[���f���̃Z�b�V�����͔��\�����債�������ɂ��̏W�܂����C�ɂȂ����B���܂�ɏ��Ȃ��ՎU�Ƃ��Ă���͍̂��邵�C���e�����߂��ăX�y�[�X��@�ނ̊m�ۂɋ�J����̂��L��Ȃ��B���̈Ӗ��ł́CISMR'99�̌���ɂ͎��I�ɂ��� �I�ɂ��K�x�ȉ������������B�u����well balance�ȃZ�b�V�����\�����v�u����܂łɏo����c��best organized�I�v�Ƃ����]���Ղ����̂��C���������K�^�������Ă����̂ł���B
�@��1��̍��ۉ�c�ł���C���O���ɂ͂��܂�A�i�E���X�����Ȃ������̂ŁC�C�O����̓��e�͊��҂��Ȃ������̂����C�����f�����܂߂�4�������傪�������̂͊�������Z�ł������B���������10�������̑��� �ȉ��傪���������C���ɔM�S�Ȋ��U�������킯�ł͂Ȃ��B�u�����������v�Ƃ����e�[�}���L����������n�߂��؋��ł���C�C�O����̈ꗬ�ǂ���̑O�Ō������� ���A�s�[�����Ă��������Ƃ������`�x�[�V���������������ƂƎv����B
�@�������삪�����オ��C�傫����������ߒ��ł́C�L��͂̂��钘���l�̑��݂�L�̓O���[�v�Ԃ̑��ݍ�p�E������� ���傫�Ȗ������ʂ������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�v����ɁC���܂���̐��̃t�B�[�h�o�b�N�������C�ǂ������ɔ��W��������̂ł���B
�@�|�X�^�[���\�ɂ��C�r�f�I�̕��p�҂��唼�������B���̏����͂܂��ȒP�����C���@�f���ƂȂ�Ɣ�������̂���������̂��C���Ȃ�̘J�͂�������B����ł��C�q���[�}���C���^�t�F�[�X��VR�̕���̉��ɂ́C���������f���E�R�[�i�[�͕s�����낤�B
�@�����Ƌ���MR�Q�[����
�@ISMR'99�́C���Ƃ���MR�v���W�F�N�g�̒��Ԑ��� ��̂���ł������̂�����C���̌��w�c�A�[�ɗ͂���ꂽ�͖̂ܘ_�ł���B
�@�ł��b����Ă�RV-Border Guards�́C����܂�MR�v���W�F�N�g�̏ے��ł�����AR2�z�b�P�[����̂����W���������̂ł���B���ۂ̃v���C���[�������̃e�[�u���̏�ʼn��z�̃p�b�N��ł�����AR2�z�b�P�[��SIGGRAPH 98�ɏo�W���đ傫�ȏ^���i�ʐ^4�j�B�V���Ԃ�1,000�g2,000�l�ȏオ�̌����C��x���_�E�����Ȃ��������߁u�ł����o�X�g�ŁC�ł������̐l���̌�����AR�V�X�e���v�Ƃ����]�����B
 �ʐ^�S�@AR2 Hockey at SIGGRAPH98 |  �ʐ^�T�@�v���C���[���猩�����i |
�@�����C�����l��������ԂƉ��z��Ԃ����L���C�����ԂőΘb�ł���V�X�e���̎���Ƃ��Ă��̃Q�[����I�̂����C�z���ȏ�̔������������B�\�����āC���W���[�ȃQ�[���@���[�J�[�����w�ɗ���ꂽ���C�e���r�ԑg�ł����グ��ꂽ�B���X�Ɖ��ǂ��d�˂Ă����܂œ��B�������J���S���҂́C����ɉ��nj^�W���������������C����ɂ�OK���o���Ȃ������BMR�v���W�F�N�g�́C���܂ł��G�A�z�b�P�[�������Ǝv��ꂽ���Ȃ���������ł���B
�@�z�b�P�[�̉��z���̓p�b�N�����ł���C�������e�[�u������i������������ԂŁj2�����I�Ȑ���̉��Ɉړ�����B�ڂ̑O�̌�����Ԃ��t���ɉ��z��ԂƂ��ė��p�ł��C�����ƕ��G�ȂRD�I�u�W�F�N�g���\���ł���̂ɁC�G�A�z�b�P�[�ɐ������Ă���̂͂��������Ȃ��B�u�Q�[����Ђ����������Ȃ�C�����ƓO�ꂵ�ăQ�[���炵���Q�[���ɁC�����Ƌ����Q�[���ɂ��Ă݂ȁv�Ƃ����̂��^�����ۑ�ł���B�������Đ��܂ꂽ�̂�RV-Border Guards�i�ʐ^5�j�ł���B
�@�l�[�~���O�̗R���́C���z��Ԃƌ�����Ԃ̋��E�ɂӂƂ������Ƃ��猊�������CVirtual������Real���ɃG�C���A���������N�����Ă���̂��CRV-Border �̌x�����i�h�q�R�j���ł����Ƃ��C�Ƃ����o�J�o�J�����z��ɂ���BAR2�z�b�P�[�̉��n���������Ƃ͂����C�v���O���~���O���n�߂Ă���Q�������炸�łł����������̂́C�悭�Ԃɍ������Ǝv���BCG�I�u�W�F�N�g��������Ԃɗ��Ƃ��e��C����������̎� �荞�݁C�������̂Ƃ̃I�N���[�W�������\���ł��C�ו��ɂ������Q�[���E�t�@���������S�����邱�Ƃ��ł����B
�@�Z���Ԃł��Ȃ�̊����x�ɒB�������̂́C���̃V�X�e���ɂ͊w�p�I�V�K���͂قƂ�ǂȂ��B����Ȃ̂ɏ��w�p�n�̎Q���҂ɂ��C���̃f�����ő�̐l�C�ƂȂ����B�R���e���g�̏[���x�C�g�[�^���V�X�e���Ƃ��ĉ��l���]�����ꂽ�悤���B���̐V�Q�[������ �̃e���r�ԑg4)�ŏЉ�ꂽ���C���̌�����w�҂������Ă���BMR�Z�p�̍ő�̎s�ꂪ��y�Y�Ƃɂ��邱�Ƃ��C���߂ăA�s�[������Ƃ���ƂȂ����B ��6���@���ʃZ�b�V�����F�n���E�b�h�̍���͍����
�@�O�^���͊��ҊO��
�@�ŏI���̌ߌ�́uFuture Entertainment and MIxed Reality�v�Ƒ肵�����ʃZ�b�V�����ł����B�A�����J���C�݂̃f�B�W�^���E�v���_�N�V�����̎В�����2�l�̍u���ɁC���{�̃}���`���f�B�A�E�X�N�[���u�f�W�^���E�n���E�b�h�v�i�ȉ��CDH�j�̊w�Z���������Ẵp�l�����_�Ƃ����\���ł��B���̃Z�b�V���������ŁC�Ɨ������V���|�W�E���̌`���Ȃ��Ă��܂����B���ہCDH�Ƃ̋��ÂŁC���̓��� �Z�b�V���������̎Q�����\�ŁC�����ʖ�����Ă��܂����B
�@�A�J�f�~�[���o���ʏ܂�������w�x�C�u�x��Rhythum & Hues�Ђ�J.�q���[�Y�В��C��NHK�w�l�́\���Ђ̏��F���x��CG�v���f���[�T�ŁC���݂̓r�o���[�q���Y�ɂ���Magic Box Production�̈ɓ������В��C������DH�ɂ̓T���^���j�J�Z������C�p�l�����_�̎i��f.���[�J�X�����f��w���̃R���s���[�^�A�j���[�V����������R.���C���o�[�O�������������Ƃ���C�G���^�[�e�C�������g�Y�Ƃ̃��b�J�CLA�̔M���z�˂��Ƒu�₩�ȕ��̍�������������܂����B�c�O�Ȃ��炱�̓����J�͗l�ł������C�ߌォ��͎Ⴂ�N���G�[�^�B�����X�Ƃ���ė��܂����BNICOGRAPH�Z�~�i�[�Ɏ������͋C�ŁC����܂ł�2�����̊w��[�h�͈�V���Ă��܂��܂����B
�@3���Ԃ̃V���|�W�E���̃G���f�B���O�Ƃ��āC�傢�Ɋ��҂����̂ł����C���̃Z�b�V�����͑�O��ł����B�uThe History and Future Direction of Visual Effects�v�Ƒ肵��J.�q���[�Y���̍u���́C�Ȃ�قǁC�w2001�N�F���̗��x����w�^�[�~�l�[�^�[�Q�x�w�W�����V�b�N�E�p�[�N�x���o�āw�^�C�^�j�b�N�x�Ɏ���VFX�̗��j���Ȃ����Ă��܂������C�������ꂾ���̂��Ƃł��B���������Ƃ̊ւ����C�����ւ̓W�]���L��܂���B���߂āw�x�C�u�Q�x�̃��C�L���O���炢�L�邩�Ǝv�����̂ɁC���������܂���B�����C�����ȉf��̒Z���N���b�v����ׂ������ŏI����Ă��܂��܂����B
�@�ɓ��������́uAugmented Reality for Enter-tainment�v�́C�b�����r�f�I���܂��܂��������̂ł����CAR�̈Ӗ�������Ă��܂����BCG���������z����\���ݏo���Ƃ����咣�ł����āC�g�������ł����������ł�����܂���ł����B
�@2001�N�͊撣���ĉ�����
�@���R�m�V����������āC�p�l�����_�͏����������܂�܂����B���R�����MR�v���W�F�N�g�̊J�n�̍�����A�h�o�C�U�����Ă����āC�����c���ƌ���������̂悤�ł��BDH�́C�ݗ�5�N�Ŗ�5,000�l�̑��Ɛ��𑗂肾���C�N���G�[�^�s���傢�Ɋ����������Ă���悤�ł��B���̊w����i�́C��N�䂪�����}���`���f�B�A�E�O�����v���ŕ\������C�ŋ߂ł�SIGGRAPH������X�ƁC���I��𑗂荞��ł���悤�ł��B
�@�}���`���f�B�A��CG�̃N���G�[�^��y�o���Ă��邱�̃X�N�[���̊w�Z������́CVR����ɂ�MR�̖����ɑ傫�Ȋ��҂������Ă�����悤�ł��B�u��҂�3D-CG�f������D���ŁC�����ȉ�� �̒��ł����ƍL�����E�Ŏg���������Ă���B������r�W�l�X�ɂȂ��邱�Ƃ��Ă���v�Ƃ��������͂ƂĂ���ۓI�ł����BVR�ɂ���MR�ɂ���C�Z�p�̘g�g���i�W����C�R���e���c���[�������Ă����N���G�[�^�B���҂��Ă���Ƃ������Ƃł��B
�@���̃p�l���X�g����́CMR�v���W�F�N�g�ɑ��āu�� �Y�Ȃ̎{��Ƀr�W�������������B�����Ƃ��܂��s���ɈႢ�Ȃ��v�u5�N���MR�Z�p���傫�ȃg�����h�ɂȂ��Ă���Ɗm�M�����v�Ƃ�������������܂����B���ҍu���҂����ɁC������Ƃ������������Ă���̂��ȂƎv���܂����C���{���̂��̋Z�p���n���E�b�h�����Ȃ点��悤�ɂȂ��ė~�������̂ł��B
�@���������J�ߌ��t�̔��ʁC�w�p���x���ƃv���_�N�V�����ł̎��p���x���ɂ́C�܂��܂��M���b�v������Ƃ̎w�E������܂����B�ł́C�u���̃M���b�v�����߂�ɂ͂ǂ�������悢���H�v���_�N�V����������͕��݊��Ȃ��̂��H�v�̎���ɑ��āC���̖��m�ȉ��Ȃ������̂��c�O�ł����B�v���_�N�V�����̎В�����͌o�c���S�ł��傤����C�����ƌ���̋Z�p�҂�I�ق����ǂ������Ǝv���܂��B
�@�Ō�ɁC�����2�N���2001�N3���ɓ����ꏊ�ŊJ�Â����|�C�����ψ����̜A���� �F�搶����A�i�E���X������܂����B����܂łɂ́C�ǂ����ď�L�̃M���b�v�����܂�̂������o�Ă��ė~�������̂ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i![]() �j
�j
���䗠�U�@���f�B�A�̃^�C�����O
�@�ؓ��݂ǂ������Ă���
�@�l�I�ɂ��o��ʂɂ��傢�ɗ͂���ꂽ�̂����C�g�������\�[�X�قǂ̌��ʂ͓����Ȃ������悤���B�p�l���X�g�ɂ�MR�v���W�F�N�g�͕]�����ǂ��������C���̐�^�̐��ɔ��������̂́C���O�ł͂Ȃ��}�X�R�~�������B
�@���ʂ̊w�p�����W��łȂ��C�A�[�g��G���^�[�e�C�������g�̃N���X�I�[�o�[������Ƃ������ƂŁC�ϋɓI�ȍL��헪�����C�v���X�����[�X���������̂����C�����͂悭�Ȃ������B�G����e���r���D�ޑ�ނ��Ǝv���̂����C�قƂ�Ǐ���Ă��Ȃ������B
�@�w���ÂȂ̂ŁC���ƃx�[�X�̃v���X�����[�X�̂悤�Ȍ֑�L�����̃R�s�[�͎��l�������ߒ��ӂ����N���Ȃ������̂����m��Ȃ��B�J�Â����l�Ƃ����̂��}�C�i�X�v���炵���B�������O���ƋL�҂̑��͉��̂��C���l�x�ǂ�����ꍇ�́C�X�ɂ܂����悤���B�x�ǂ̋L�҂́C���[�J���j���[�X���S�Ő�[�Z�p�ɂȂNj����������Ȃ�����ł���B
�@����Ȃ����̂́C���̒��ɑ��݂��Ȃ��Ɠ������Ƃ������C��ނɗ��Ȃ����͕̂̉\������Ȃ��BPC�n�̎G����E�F�u�j���[�X�ŔM�S�ȂƂ��낪���������C���W���[���f�B�A������ė��Ȃ��B����ł��C�O���ŏq�ׂ��悤�ɁC��䎁�̐V���ړ��Ăɉ��Ђ�����ė����̂����C�Z�p�f���̃R�[�i�[��MR���c�A�[�ɂ͌����������Ȃ������B
�@���܂��܍ŏI���̃p�l�����_�ɋ����킹���L�҂́C�O���l�p�l���X�g�Ǝi��̌��܂ɖڂ��J�����炵���B�}�ɁCMR�v���W�F�N�g�̐���
��������Ƃ����B�O���M�S�ɗU�����̂ɖ��������̂ɂł���B�����̉��l���f�ł͂Ȃ��C�O���l���J�߂�Ƌ}�ɕ]�����オ��͓̂��{�̃W���[�i���Y���̔߂�������ł���B������܂�1�̕]����Ȃ̂��낤���C��Ȃ��I
�@�ɓ����̊��߂ŁC���TV�ƊE������Q�[���\�t�g��Ђ�������낼��ƌ��w�ɂ���ė����B���D�̖ؓ��݂ǂ�܂ł��CRV-Border
Guards�����ɗ����̂ɂ͋������B���郁�f�B�A�����グ��ƁC��������đ��̃��f�B�A�����������B���́u���Â鎮�v�͑傢�ɃA�e�ɂ����̂����C���X�^�C�����O���������Ƃ������Ƃ��B�p�l�����_�͂܂�Ȃ��������C�p�l���X�g������
�I�ɍL����̃g���K�[�ɂȂ��Ă��ꂽ�悤���B
�@�����ă}�X�R�~�������邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ����C�w��Ȃǂɂ͗��Ȃ��ٕ���̐l�����ɐV�����Z�p�̉\����m���Ă��炤�ɂ́C���f�B�A�ɗ���̂��������B�ߔM�����邪�C�₦�߂��đ��݂���m���Ȃ��̂��L��Ȃ��B�}���`���f�B�A�E�t�B�[�o�[�̃o�u�������̂m�V���𒆐S�Ƃ����W���[�i���Y���͊��S�ɂ��̌��ǂ̒��ɂ���B�S�����Z�s���Ǝ��Ƃ̊�@�������ȊO�ɔ\�͂Ȃ����̂��B���������Z�p�f�t���̎���ɂ����C�����m���̂悤�Ȋy�ώ�`�̃A�W�e�[�^���K�v�Ȃ̂����m��Ȃ��B
�@�����Ȃ��Ђ��݂����m��Ȃ����C���N��ɂ��̔��������āC�܂��܂��ߑ�]���ƍs���߂����\�w�I�ȕ�����ȂƋ����̂ł���B�i![]() �j
�j
�@�܂Ƃ߂Ƃ����A
�@![]() Dr.SPIDER�@���z�Q���҂̆��́C���Ȃ��̊��z�ƈ��
�Q���҂̃A���P�[�g���ʁ{���ō��܂������C���̊�݂͂��܂��s���܂������ˁH
Dr.SPIDER�@���z�Q���҂̆��́C���Ȃ��̊��z�ƈ��
�Q���҂̃A���P�[�g���ʁ{���ō��܂������C���̊�݂͂��܂��s���܂������ˁH
�@![]() Yuko�@�����ł͕]�����ɂ����̂ł����C���ϑ��Ƃ����C�͂��܂��B
Yuko�@�����ł͕]�����ɂ����̂ł����C���ϑ��Ƃ����C�͂��܂��B
�@![]() �@���̃V���|�W�E���̂��߂ɍł��������l���C�e�̎��s�ψ����Ƃ��Ă̊��z�͂������ł����i�j�B
�@���̃V���|�W�E���̂��߂ɍł��������l���C�e�̎��s�ψ����Ƃ��Ă̊��z�͂������ł����i�j�B
�@![]() �@���Â����������̎Q���͊y�ł����Ǝ������܂����i�j�B�F���܂̂������ŗ��h�Ȗ{���c�����̂ƁC�u�^�c���f���炵�������v�Ƃ̌��t�Ղ����̂͊����������ł��i�����Ŏv�킸�܂��ށc�c�Ƃ����̂̓E�\�I�j�B���{�̃��x�������ĂɏЉ�邨���ɗ������Ƃ͎v���܂��B
�@���Â����������̎Q���͊y�ł����Ǝ������܂����i�j�B�F���܂̂������ŗ��h�Ȗ{���c�����̂ƁC�u�^�c���f���炵�������v�Ƃ̌��t�Ղ����̂͊����������ł��i�����Ŏv�킸�܂��ށc�c�Ƃ����̂̓E�\�I�j�B���{�̃��x�������ĂɏЉ�邨���ɗ������Ƃ͎v���܂��B
�@![]() �@�n�C���x���Ɗ������̂́C�����ȓ��_�C�������ƒ����l�����ތ���
�C�����Ɨ����̏[���x�C���X�̐D��Ȃ������]���ł��傤�B���ꂪ����臒l���āC�l�X�̈�ۂɋ����c�����Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�n�C���x���Ɗ������̂́C�����ȓ��_�C�������ƒ����l�����ތ���
�C�����Ɨ����̏[���x�C���X�̐D��Ȃ������]���ł��傤�B���ꂪ����臒l���āC�l�X�̈�ۂɋ����c�����Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@![]() �@���ꂾ����������ゾ�ƁC��ۂɎc��c��Ȃ���0�C1�ł��ˁB
�@���ꂾ����������ゾ�ƁC��ۂɎc��c��Ȃ���0�C1�ł��ˁB
�@![]() �@���Y�I������I���Ƃ������
������܂��B�_��������Ɉ��p���ꂽ��C���̃O���[�v�ɉe����^����悤�ȃf���́C���Y�I�Ȍ�������
�ł��B����ɑ��āC���Ԃ��g���āC����v�Z�������R�̂悤�Ɏg���āC�N�̃v���X�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂�����I�����ł��BGNP�������グ��ȊO�C���̌���
���Ȃ����Ȗ����I�Ȋw��\�����̒��̑唼�ł��B
�@���Y�I������I���Ƃ������
������܂��B�_��������Ɉ��p���ꂽ��C���̃O���[�v�ɉe����^����悤�ȃf���́C���Y�I�Ȍ�������
�ł��B����ɑ��āC���Ԃ��g���āC����v�Z�������R�̂悤�Ɏg���āC�N�̃v���X�ɂ��Ȃ�Ȃ��̂�����I�����ł��BGNP�������グ��ȊO�C���̌���
���Ȃ����Ȗ����I�Ȋw��\�����̒��̑唼�ł��B
�@![]() �@�܂�����Ȍ��݂������āC�����܂���B
�@�܂�����Ȍ��݂������āC�����܂���B
�@![]() �@����ς莄�͌�����i�j�B������ł��B���������Ő���͂��Ă��C�F�����̂��Ƃ��Ƃ͎v���Ă��Ȃ�����i�j�B
�@����ς莄�͌�����i�j�B������ł��B���������Ő���͂��Ă��C�F�����̂��Ƃ��Ƃ͎v���Ă��Ȃ�����i�j�B
�@![]() �@�R�X�g�p�t�H�[�}���X���ǂ������Ƃ̕]�������������̂ł����C���������łȂ��C���ԓI�ɂ��[�����Ă����Ƃ̂��Ƃ̂悤�ł��B
�@�R�X�g�p�t�H�[�}���X���ǂ������Ƃ̕]�������������̂ł����C���������łȂ��C���ԓI�ɂ��[�����Ă����Ƃ̂��Ƃ̂悤�ł��B
�@![]() �@�w����W����E�u�K����������邩��C������O��̂Ȃ����ԗ��p���ł��D�܂��̂ł��傤�B�w��͑������ė]��Y�ƊE�̖��ɗ����Ȃ����CPC��C���^�[�l�b�g�n�̓W������������āC���I��������Ȃ��Ă��܂��ˁB
�@�w����W����E�u�K����������邩��C������O��̂Ȃ����ԗ��p���ł��D�܂��̂ł��傤�B�w��͑������ė]��Y�ƊE�̖��ɗ����Ȃ����CPC��C���^�[�l�b�g�n�̓W������������āC���I��������Ȃ��Ă��܂��ˁB
�@![]() �@����CIF�V���[�Y���ӔC�d��ł��ˁi�j�B
�@����CIF�V���[�Y���ӔC�d��ł��ˁi�j�B
�@![]() �@�ł́C2��ɂ킽���ē��֘b��������ISMR'99���猩�������͂������ł����H
�@�ł́C2��ɂ킽���ē��֘b��������ISMR'99���猩�������͂������ł����H
�@![]() �@�ʒu���킹��掿���킹�̌����������ɐi��ł���Ƃ�����ۂ����l�����������悤�ł��B�v�����ȏ�ɁC���������g���������ƁB���ꂩ��C�A�E�g�h�A�ł̗��p�Ɍ����āC�������n�܂��Ă���̂��͋����g�����h�Ɗ������܂����B
�@�ʒu���킹��掿���킹�̌����������ɐi��ł���Ƃ�����ۂ����l�����������悤�ł��B�v�����ȏ�ɁC���������g���������ƁB���ꂩ��C�A�E�g�h�A�ł̗��p�Ɍ����āC�������n�܂��Ă���̂��͋����g�����h�Ɗ������܂����B
�@![]() �@���ꂩ��L�т�Ƃ������C�L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��e�[�}�ł��ˁB���o�C���C�E�G�A���u���́C�ԈႢ�Ȃ����̒��̗���ł�����C�A�E�g�h�AAR/MR�̌����l���������邱�Ƃł��傤�B
�@���ꂩ��L�т�Ƃ������C�L���Ȃ���Ȃ�Ȃ��e�[�}�ł��ˁB���o�C���C�E�G�A���u���́C�ԈႢ�Ȃ����̒��̗���ł�����C�A�E�g�h�AAR/MR�̌����l���������邱�Ƃł��傤�B
�@���āC�Ō�ɂ����A������܂��ˁB
�@![]() �@�n�C�BCIF3�V���[�Y����2���
�@�n�C�BCIF3�V���[�Y����2���![]() ���߂Ă��܂������C���̍����Ō�Ɉ��ނ��邱�ƂɂȂ�܂����B
���߂Ă��܂������C���̍����Ō�Ɉ��ނ��邱�ƂɂȂ�܂����B![]() ���Ƃ��Ă͒Z�����Ԃł������C�L��������܂����B
���Ƃ��Ă͒Z�����Ԃł������C�L��������܂����B
�@![]() �@ISMR'99�ŔR���s���āC���Ƃ͕���
�̎�w�ɂȂ�Ƃ����킯�ł����i�j�B�܂��C�ɂ������āC�Q�X�g�o�����ĉ������B
�i
�@ISMR'99�ŔR���s���āC���Ƃ͕���
�̎�w�ɂȂ�Ƃ����킯�ł����i�j�B�܂��C�ɂ������āC�Q�X�g�o�����ĉ������B
�i![]() �j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Â��C�ȉ������j
�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�Â��C�ȉ������j


